お寺や神社には御朱印という物があるのを皆さんご存知でしょうか?
御朱印とは、お参りに行った際に手帳のようなものや紙に文字を書いてもらえるものとなっています。
社寺仏閣をお参りするごとに違うデザインの御朱印を集める方も多いかと思いますが、御朱印の歴史や、お寺と神社の関係について知っている方は少ないのでは?と思います。
そこで今回は『御朱印に関する歴史とお寺、神社の関わり』についてご紹介します。
御朱印には何が書かれているの?

御朱印とは朱色の印鑑が押されたもののこと。多くはその印鑑と共に、社寺仏閣の名前や参拝した日付を手書きで書いてもらえます。
最近では、神社やお寺に由来する聖獣や伝説の生き物などのイラストが描かれていたり、期間限定の特別な御朱印などが用意されていたりします。
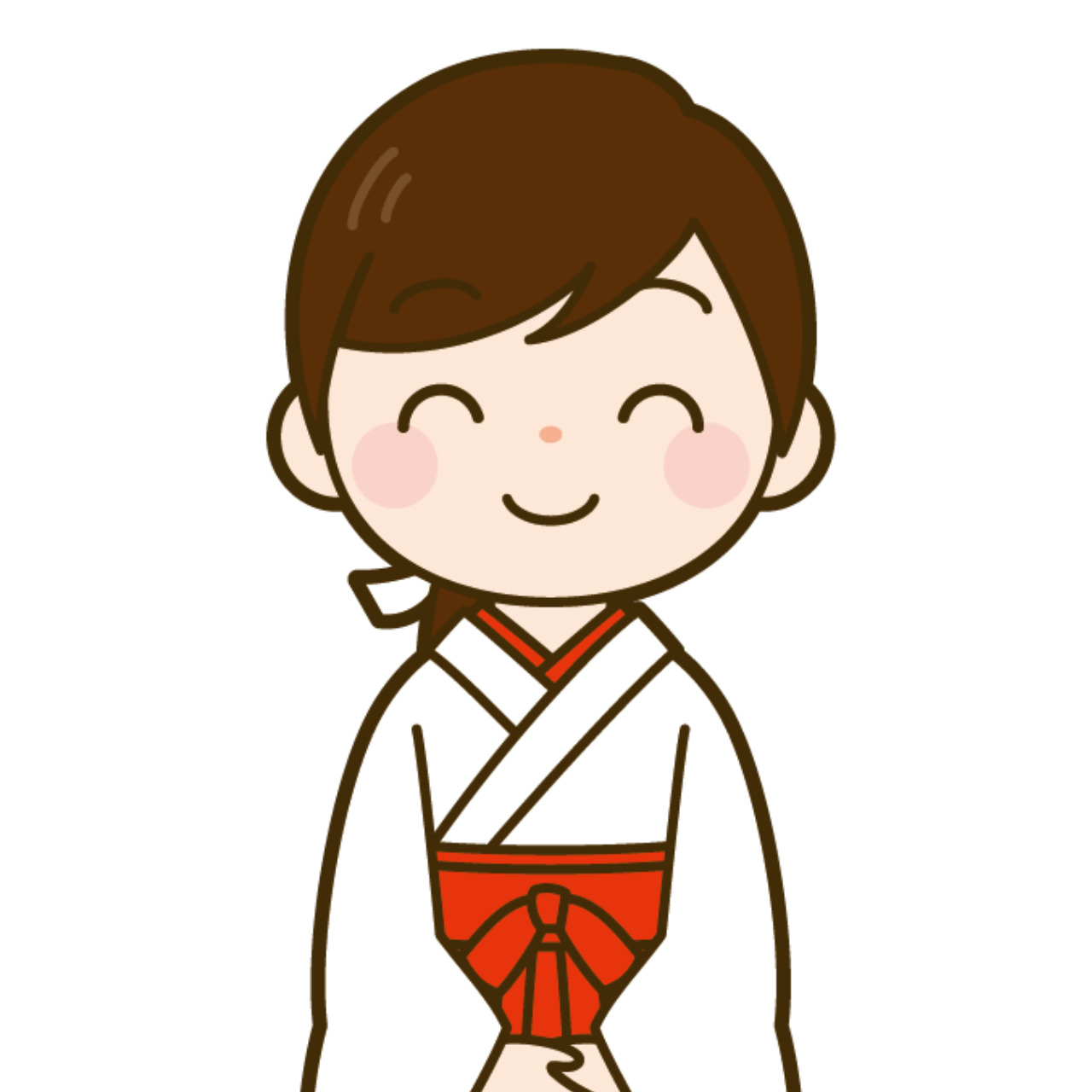
最近では御朱印にQRコードの判子が押されたものもあるみたい。
スマホで読み込めばいつでもその参拝した寺社のHPにアクセスできるんだって。
とっても便利!
御朱印帳の起源と、もらう目的とは?
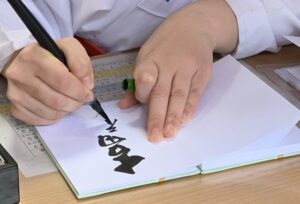
御朱印の始まりは明確な証拠が残っていない為、はっきりとした由縁はありません。
しかし、諸説がいくつか見つかっています。
とある一説によると、古墳時代の大和朝廷で行われていた印章制度が起源となったのだそう。当時から政治的、文化的、宗教的に朝廷(天皇)と寺社は深く関わりがあり、地方行政や税制を行っていた際に、印章制度が行われていたと言われています。
また、別の一説には、江戸時代に行われていた修行で六十六部廻国聖というものが御朱印の起源とも言われています。これは今の御朱印集めに少し似ていて、修行者が日本全国の66カ国を渡り、それぞれの国の代表する寺社の1カ所で法華経の一部を納経していたことが起源とも考えられているのだそう。納経するとその証明に御朱印が納経帳に記されていました。
明確な起源ははっきりとはしていませんが、いずれも御朱印は寺社との関わりを証明するものであったのは確かです。
その為、現在でも御朱印はお参りした証拠としてもらうので、いつどこで参拝したのかが分かるように記してあります。
実は御朱印帳の共有を嫌う社寺仏閣がある?

結論からお伝えすると、そもそも神社とお寺には宗教の違いがあるので、御朱印帳を統一してしまうと、嫌がられることがあります。
とはいえ、実際共有していたとしても、文句を言われるという頻度は比較的少ないと言われています。
最近ではコロナ禍だったこともあり、御朱印帳に直接書き込むスタイルではなく、書き置きスタイルで授与する場所が増えています。そのため、ますます断られる確率は低くなっているのではないでしょうか。
では一体、どこの神社やお寺が嫌がるのか。
それは僧侶や神職の信念、信仰心によって異なります。
そもそも神社とお寺では宗教が違うことを忘れてはいけません。神社もお寺も日本人の生活には欠かせない存在ですが、神社は神道を信仰し、仏教はインドから伝わったとされる仏様を信仰しています。
どうして違う宗教なのに混同してしまうのか。また、どうしてそれを良しとしているのか?これは日本ならではの独特な文化だと言えます。
簡単にいうと元々日本には神道があり、その後インドから仏教がやってきました。2つの違う宗教が最初からうまく共存していた訳ではなく、過去には寺院が建立される際に一部の神社が取って代わられたり、その後神仏習合で一部の神社とお寺が一緒になるも、明治時代には神仏分離政策によって神社と仏教は分離することになりました。
そんな歴史をたどりながら、神社もお寺もお互いを尊重し、我々の生活の中で共存するようになりました。
もちろんしっかりとした信仰心のもと、社寺仏閣へ参拝に行く方もいらっしゃると思いますが、ご利益で判断したり、家からの距離でどこに行くか決めている人も多いと思います。
日本の歴史からそうした考えも受け入れられてきましたが、やはり出来るなら、それぞれの由来や考え方などを理解した上で参拝できたらいいですね。
御朱印帳の共有を嫌がる寺社の見分け方

神社やお寺で同じ御朱印帳を使っていいか、確認する方法をご紹介します。
- 事前に問い合わせ:訪れるお寺や神社のウェブサイトや連絡先を確認して、問い合わせをすることが一番確実な方法です。電話やメールで直接問い合わせて、「神社あるいはお寺と共通の御朱印帳を持参してもいいか」と尋ねることができます。
- 受付や案内所で確認する:お寺に到着した際に、受付や案内所で御朱印に関する情報を尋ねることができます。スタッフがルールを教えてくれることがありますので、丁寧にお尋ねください。
- 御朱印帳の掲示を確認する:お寺の境内や拝観エリアには、御朱印に関する案内が掲示されていることがあります。共通の御朱印帳の使用についてのルールや注意事項が書かれていることがありますので、探してみてください。
- 他の参拝者に尋ねる:お寺で御朱印を受け取る際に他の参拝者が共通の御朱印帳を使っているかどうかを見て、その参拝者に尋ねることもできます。ただし、他の参拝者の行動を見て結論を出す場合は、誤解を避けるために確認が必要です。
せっかくお参りをするなら、お寺や神社のルールを尊重して行きたいですね。
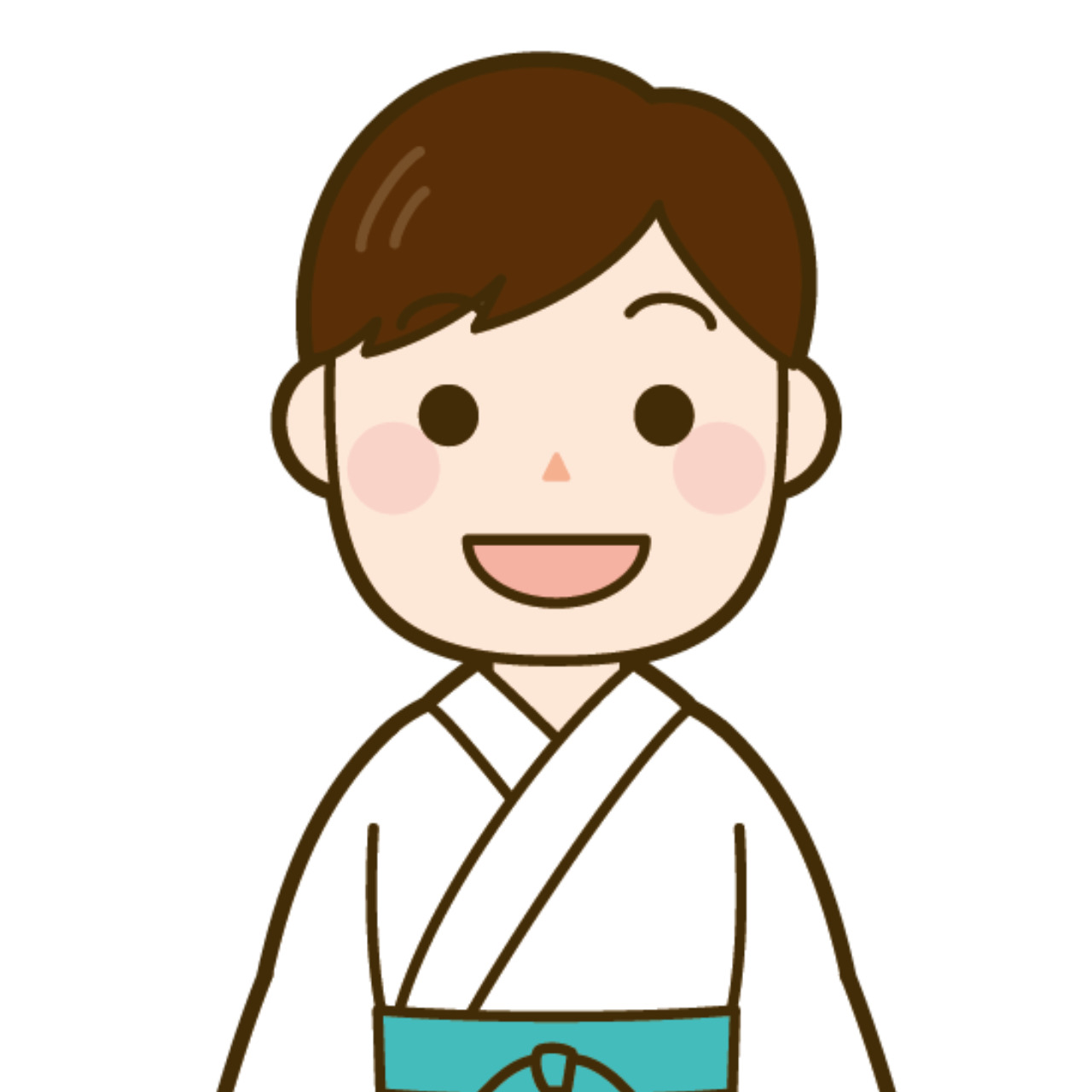
事前に電話をするのはハードルが高い…という人は、当日受付で確認するといいかもしれないですね!
こちらの記事もおすすめ✨
まとめ
本記事では、『御朱印に関する歴史とお寺、神社の関わり』についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
いつも何気なく行っていた神社やお寺も、全く別の宗教であることがわかりましたね!
御朱印集めが趣味という方も多くなっている昨今。日本の神々は他の宗教に比べて寛容ではありますが、それでも違う宗教の御朱印帳を持っていくのは失礼にあたることも…。
今一度マナーを見直すことで、改めて神聖な気持ちで社寺仏閣にお参りができるといいですね。



コメント