神社の境内にあるものと聞いてイメージできるのは、きっと鳥居、狛犬、御神木…とこの辺り。
大きな神社だと案内マップなどに「手水舎」や「参道」など、しっかりと名称が記されていますが、「どういうものなのか難しくてイマイチ理解できない!」と思う人も多いですよね。
そこで本記事では、「神社にあるものの名称一覧」を意味と一緒に超わかりやすくご紹介します。
※こちらは前編です。
続きは『《後編》神社の境内にあるものの名称一覧!超わかりやすい説明付き!』をご覧ください。
まず神社に行くと目に入るもの
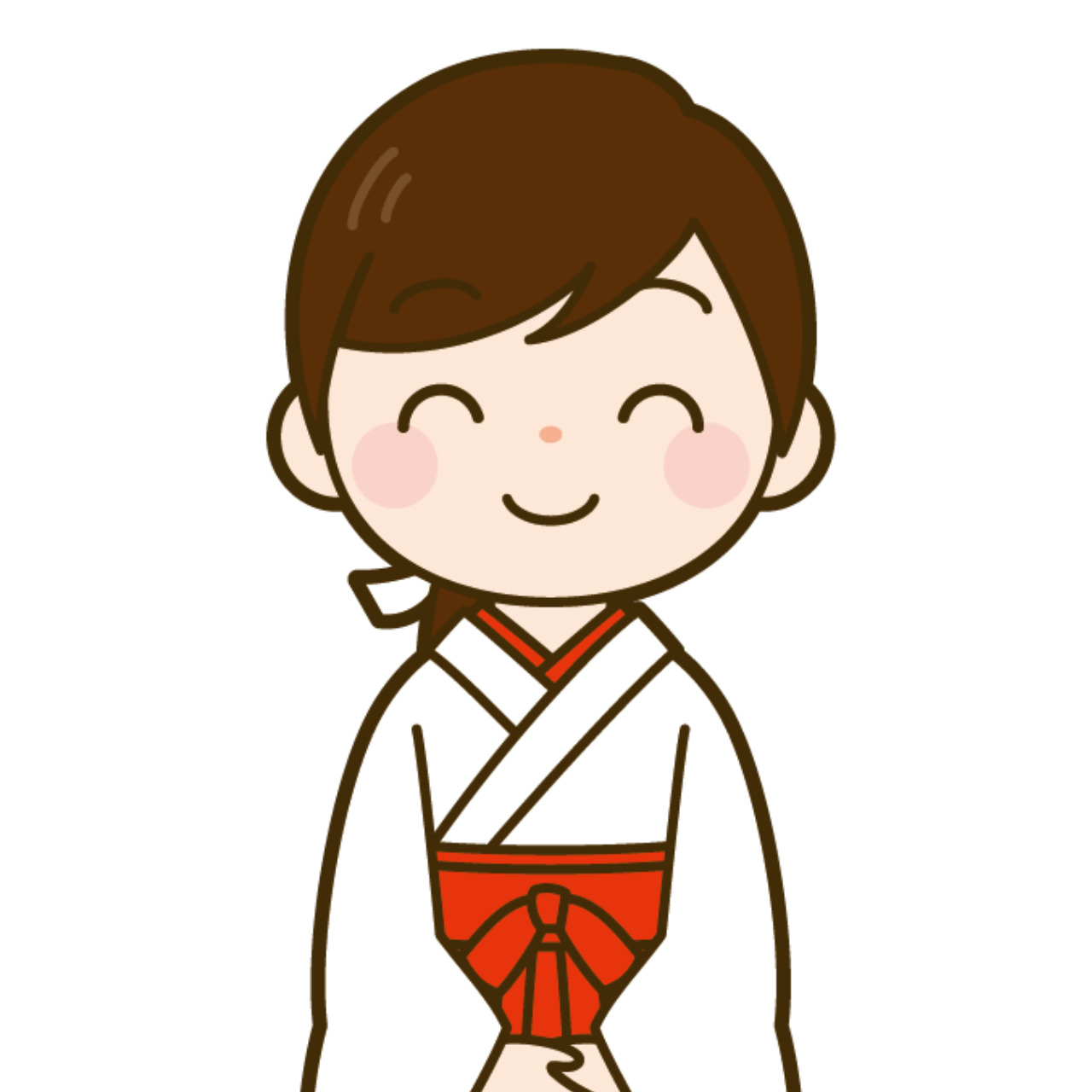
神社の境内(敷地)にあるものには必ず意味があって建てられています。
「なぜ?」を解消して、より楽しくお参りしましょう!
鳥居(とりい)

鳥居は神社にはほぼ必ず備わっているもので、私たちの住む世界と神様の住む世界を繋ぐ役割を果たします。
神社とお寺の違いはこの鳥居の存在。
人間の家でいう玄関のような場所にあたるので、くぐるときはお辞儀(挨拶)をすると丁寧でよいでしょう。
また、鳥居は大きく分けて2種類あり、鳥居上部の横柱がまっすぐになっている神明鳥居、鳥居上部の横柱の両端が上に反っている明神鳥居があります。
神社によって形や色が異なるので、違いを見つけるのも楽しみの1つですよ。
社号標(しゃごうひょう)

神社の入口にある石柱のことで、神社の名前や国の保護を受けた際にもらえる専用の名前のようなものが刻まれています。
シンプルに「〇〇神社」と彫られているものもあれば、「式内社〇〇神社」「官幣大社〇〇神社」と格式が表されているものも。
ちなみに社号標に「〇〇神宮」とあれば、神社の中で一番レベルが高い神様の家だということになります。
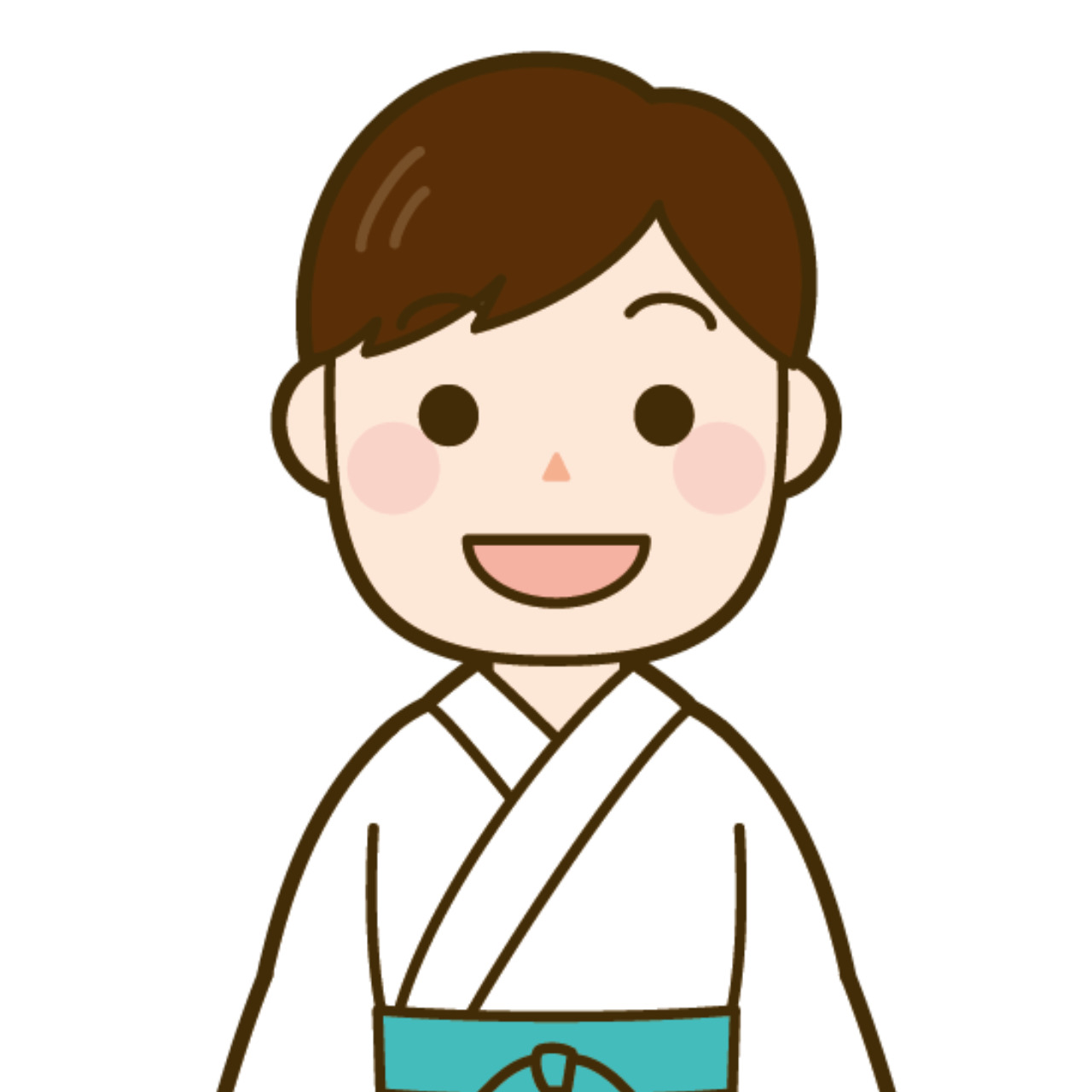
レベルの高い順から
神宮>宮>大社>大神宮>神社>社
ぜひお参りの際に見てみてください!
神門(しんもん)

鳥居や社号標と同じように神社の入口に設けられているもの。
あるところと無いところがありますが、神様の家の玄関門という認識でOKです。
一階部分と二階部分の両方に屋根が付いている場合は「二重門」、二階部分だけに屋根があるものは「楼門」と呼ばれます。
参道(さんどう)

鳥居をくぐった後に通るメイン道のこと。
砂利が敷かれていたり、石が並べられていたりと形はさまざまですが、お参りの際はこの道を通るとよいでしょう。
ちなみに参道の真ん中は神様の通り道だといわれているので、気にする方は端を歩くのがおすすめです。
灯籠(とうろう)

昔ながらの照明器具。
近年では電気タイプになっていますが、昭和ごろまでは中にロウソクを入れて明かりをともしていました。
石でできている灯籠は「献灯」とも呼ばれ、足元には個人の名前が彫られていることも。
これは地元の人やお参りをしてご利益があった人が、お礼の意味を込めて神社に捧げている可能性が高いです。
鳥居をくぐると見えてくるもの
制札(せいさつ)

戦国時代よりある制札は、もともと町の人に“禁止事項”をアピールするために立てられていたもの。
しかし、神社の中にあるものは主に由緒(なぜこの神社ができたのか)やお祭りなどの情報が記されており、掲示板のような役割を果たしています。
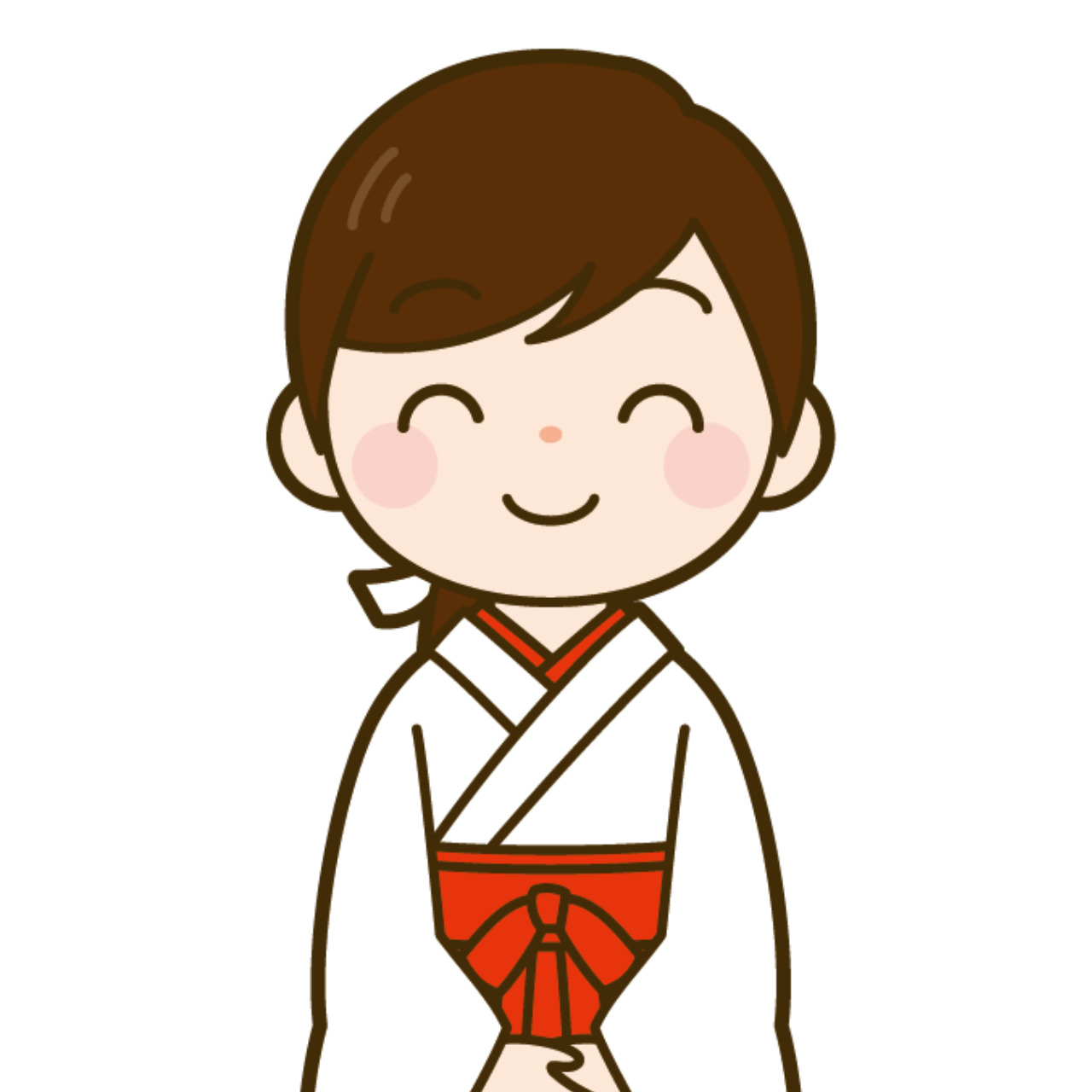
神社の貴重な歴史や、お参りした人にどのようなご利益があるのかなどが書かれています。
タメになるので、ぜひチェックしてみてくださいね!
御神木(ごしんぼく)

神様が宿る木として「神依木」とも呼ばれています。
古くから境内に根付いているので巨木に育っていることが多く、しめ縄が巻かれていたり、周囲に柵が施され、特別扱いされています。
ナギやモチノキ、スギなどの植物が御神木として祀られているケースが多いです。
玉垣(たまがき)

神社の敷地の周りや境内の建物を区切るために作られたもので、「瑞垣」とも呼ばれています。
鳥居が神様の家の玄関なら、玉垣は神様の家の外壁のような役割を果たしています。
木製のものから石でできたものなど、素材は限定されておらず、寄贈した人の名前が彫られている場合も。
手水舎(ちょうずや/てみずや)

鳥居と本殿との間にあり、身を清める場所として設けられているもの。
日本の神様は「清らかさ」を求めているので、お参りをする前には手や口をゆすぎ、穢れを落とす必要があります。
流れ出ている水を柄杓と呼ばれる道具ですくい取り、自身の浄化を行ってください。
近年ではコロナ禍なこともあり、手水舎の使用禁止や口ゆすぎの禁止が定められているところがあるので、神社の意向に沿いましょう。
狛犬(こまいぬ)

お参りをする本殿の横や参道の両脇に1匹ずつ置かれている狛犬は神様の使いで、魔よけの役割を果たしています。
神社という神域に魔物や妖怪などのよくないものが入り込まないよう、見張っている番犬のようなものですね。
鳥居をくぐった正面から右側の口を開けている狛犬が「阿」、左側の口を閉じている狛犬が「吽」。
また、神社によっては猿や狐、牛や兎といった別の動物像が神様の使いとして定められていることもあります。
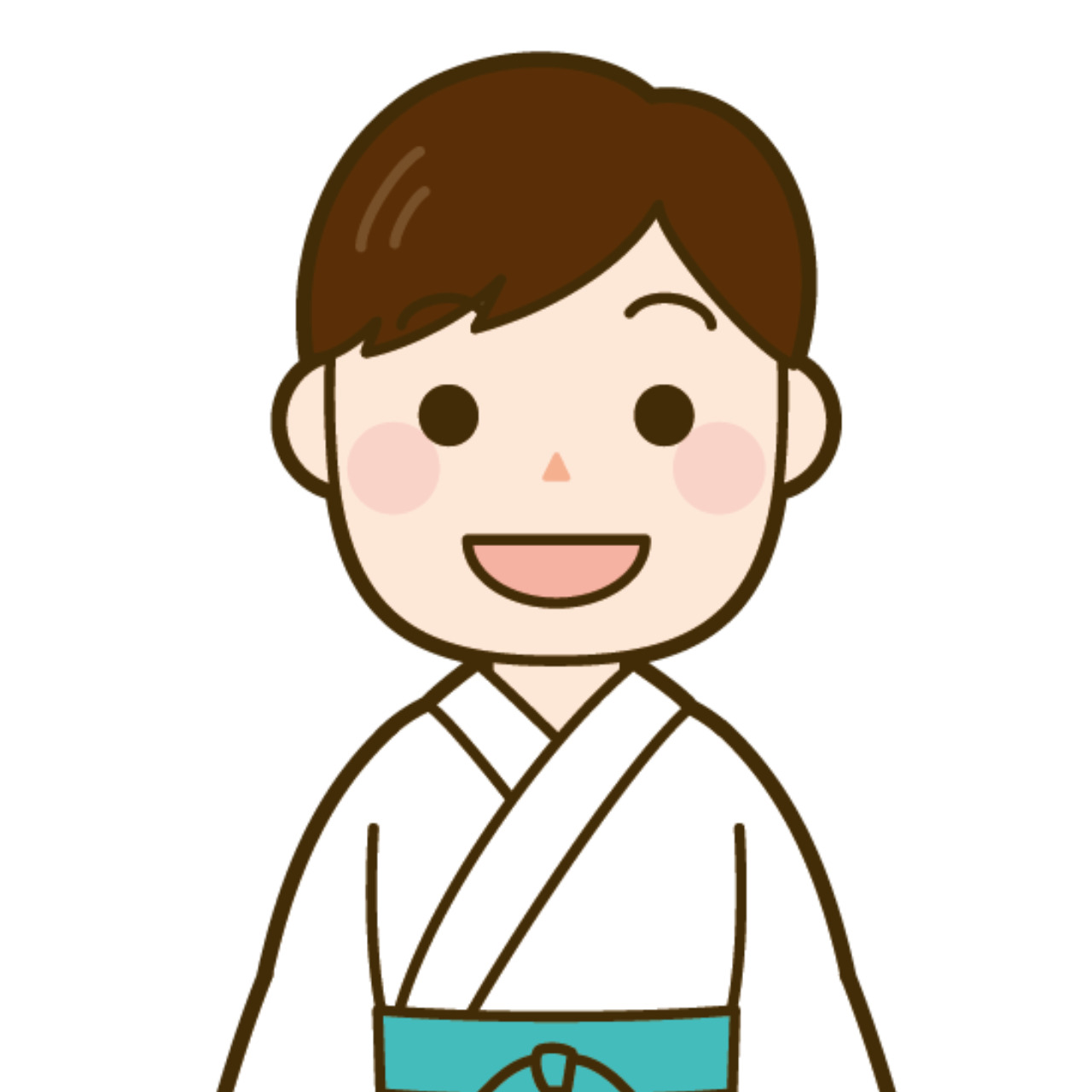
京都の有名な伏見稲荷大社は狐、北野天満宮だと牛がお出迎えしてくれますよ。
神馬(じんめ)

古くから馬は神様が願いを叶えてくださる際に乗ってくるものとされてきました。
日本の伝承によると、神社で願い事をするときには馬を捧げものとして奉納していたのだそう。
今は飼育が難しいこともあり、神馬像や絵馬を用いている場所がほとんどです。
一般的には白馬が神馬として選ばれることが多く、現代では三重県の伊勢神宮など、大きな神社に行くと生きた馬が見られることもあります。
※こちらは前編です。
本殿や授与所についてまとめた続きは『《後編》神社の境内にあるものの名称一覧!超わかりやすい説明付き!』をご覧ください。
まとめ
今回は「神社にあるものの名称一覧《前編》」をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
神社によってあるものとないものがありますが、知っておくと神様や宮司さんに失礼のないようにお参りができます。
知っておいて損はしないので、ぜひ観光や初詣の際は参考にしてみてくださいね!



コメント