私たちの生活において、神社やお寺はとても馴染み深いもの。
信仰深い訳ではないけれど、人生の節々でお参りをする事があると思います。
例えば、初詣、お墓参り、合格祈願、交通安全、安産祈願…等々。
そんな時、『寺社』や『社寺』と言っているのを聞いたことはありませんか?
同じ事を言っているのに人によって違う言い方をするなんてなんだか不思議ですよね。
そこで、「『寺社』や『社寺』実際に何がどう違うのか」どっちが正しいのかをご紹介します!
「社寺」は神社、「寺社」はお寺として
結論からお伝えすると、神社の考えを主体に『社寺』と呼び、仏教の考えを主体に『寺社』と呼ぶようになったと考えられています。
日本の民族的な信仰を主とした「神道」と、仏様の考えを見習いましょうという「仏教」では、信仰しているものや考え方も違います。
しかし、神道には八百万の神、仏教もまた釈迦如来を始め様々な仏様がいることから、神道と仏教の2つは「多神教(複数の神様を信仰していいよ)」という考えを持っています。
そのため私たち日本人は、古来より自然にあるもの全てに神様を感じていたたことから、仏様も神様と捉えることが出来ました。
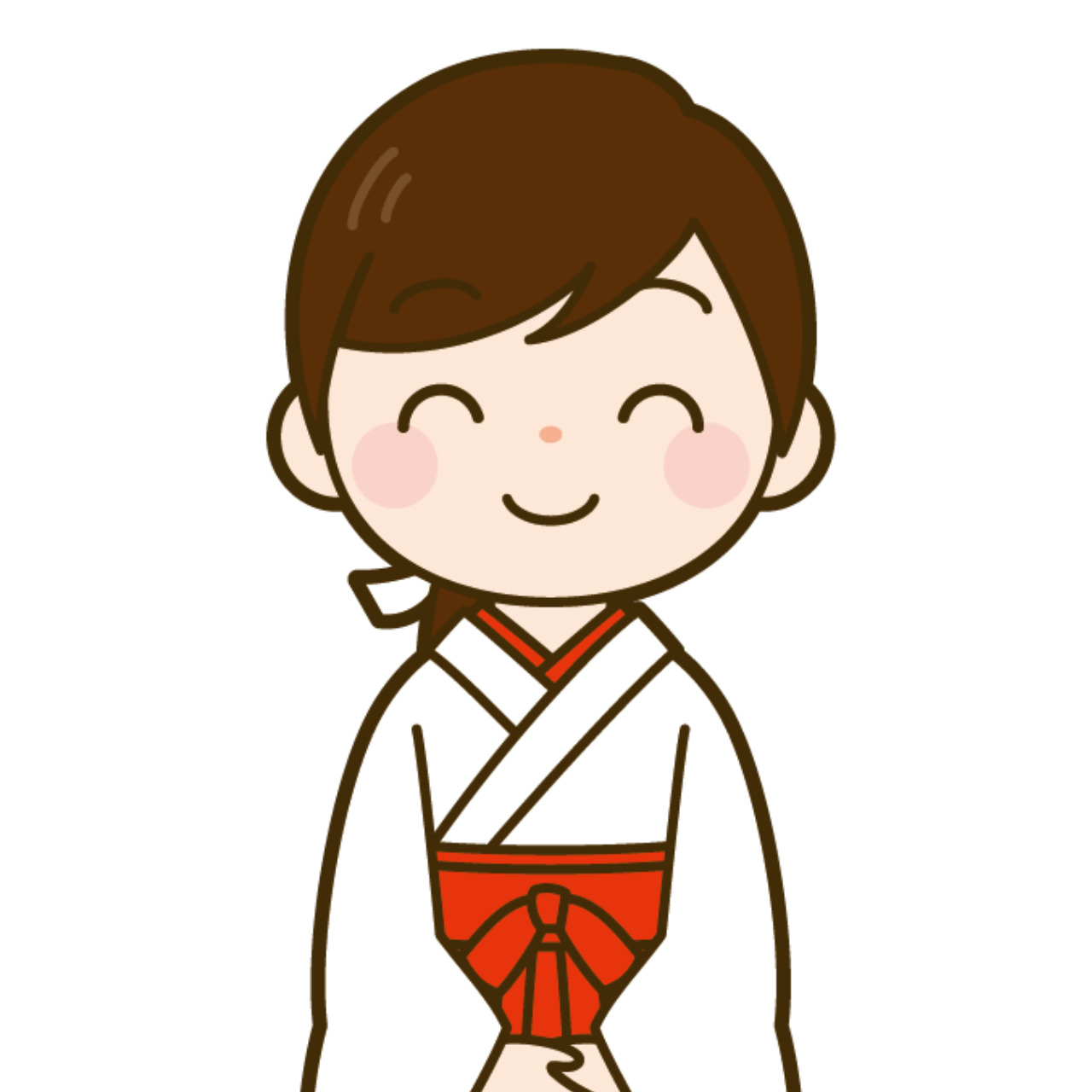
一説では、
仏様が日本にやってきた際に人々が受け入れやすいように日本の神様の姿を借りて現れたという話もあります。
神社とお寺の歴史
では、どのように信仰の違いがあるのか、神社とお寺の歴史について振り返ってみましょう!
神道は自然崇拝を行ってきた

建造物:神社
日本古来より伝わる神話がもとになっています。
まだ地上に島がなかった頃のお話。国生みの神、イザナギとその妻となるイザナミが天沼矛(あめのぬぼこ)と言う槍で島を作り日本の島ができました。
その島でイザナミはたくさんの神々を生みました。神々にはそれぞれ役割が与えられ、その中でも農業の神であるニニギにより、稲作が盛んに。
縄文時代前後の日本の人々は、自然の恵みや脅威を常に感じ、また、それを神様の力と信じ、神様が宿るものとして祀るようになりました。
また神道には仏像など拝む対象物は無く、岩や木、滝など目に見えるものから、病や風など目に見えないものまでを御神体として崇拝。
次第に神聖な場所とそうでない場所との区別をする為に鳥居や囲いが立てられるようになり、現在の神社ができたと言い伝えられています。
神道には教えというものは無く、古代の人たちの知恵や習慣によって、自然と共に生きる道を自問自答しながら形成してきました。
仏教 仏様を信仰

建造物:お寺
縄文時代後期頃、インドの周辺で釈迦という人が生まれました。
父は国王だったので釈迦もいずれ国王になるはずでしたが、ある時『生、老い、病、死』を目の当たりにします。
そこで、人生を歩む上で逃れられない苦しみがあると知り、絶望を抱いた釈迦は進むべき道を探すため修行に出ました。
長い年月に渡る修行を行い悟りを開いた釈迦は、煩悩を捨て、苦しみを克服して生きる方法を説きました。
そのため、仏教には経典があり、仏像に仏様が宿ると考えられています。
仏教の伝来

仏教の伝来には諸説ありますが、538年頃に百済(当時の朝鮮国の中にある国の1つ)の王によって仏像と経典が伝来したとされています。
仏教は次第に日本に広まり、飛鳥時代には政権に影響を与えるようになりました。
そして当時の政治家、蘇我馬子と、天皇家と同じく天孫降臨(天照大神の子孫)の逸話を持つ物部守屋が対立し、争うことになります。
物部守屋はとても強く、蘇我馬子は3度挑むが、勝つことはできませんでした。
しかし、蘇我馬子側についていた天皇家である聖徳太子が、仏教の四天王の像に祈り、木で刻んだ四天王像を頭に付けたことによって蘇我馬子が勝利したとされます。
その後、かの有名な聖徳太子により法興寺が建てられ、日本での仏教がさらに盛んになりました。
神仏習合
神道と仏教をひとつに
その後、奈良時代頃には神仏習合(神道と仏教がそれぞれにお互いを解釈し、同一視し進化)し、お互いの要素を区別することなく、同じ敷地内にお寺や神社を設けるようになりました。
また、人々の暮らしにも仏教は浸透していき、ご先祖様の供養をしたり、家に仏壇を置くようになったりしたのです。
その結果、神社の考えを主体に『社寺』と呼び、仏教の考えを主体に『寺社』と呼ぶようになったと考えられます。
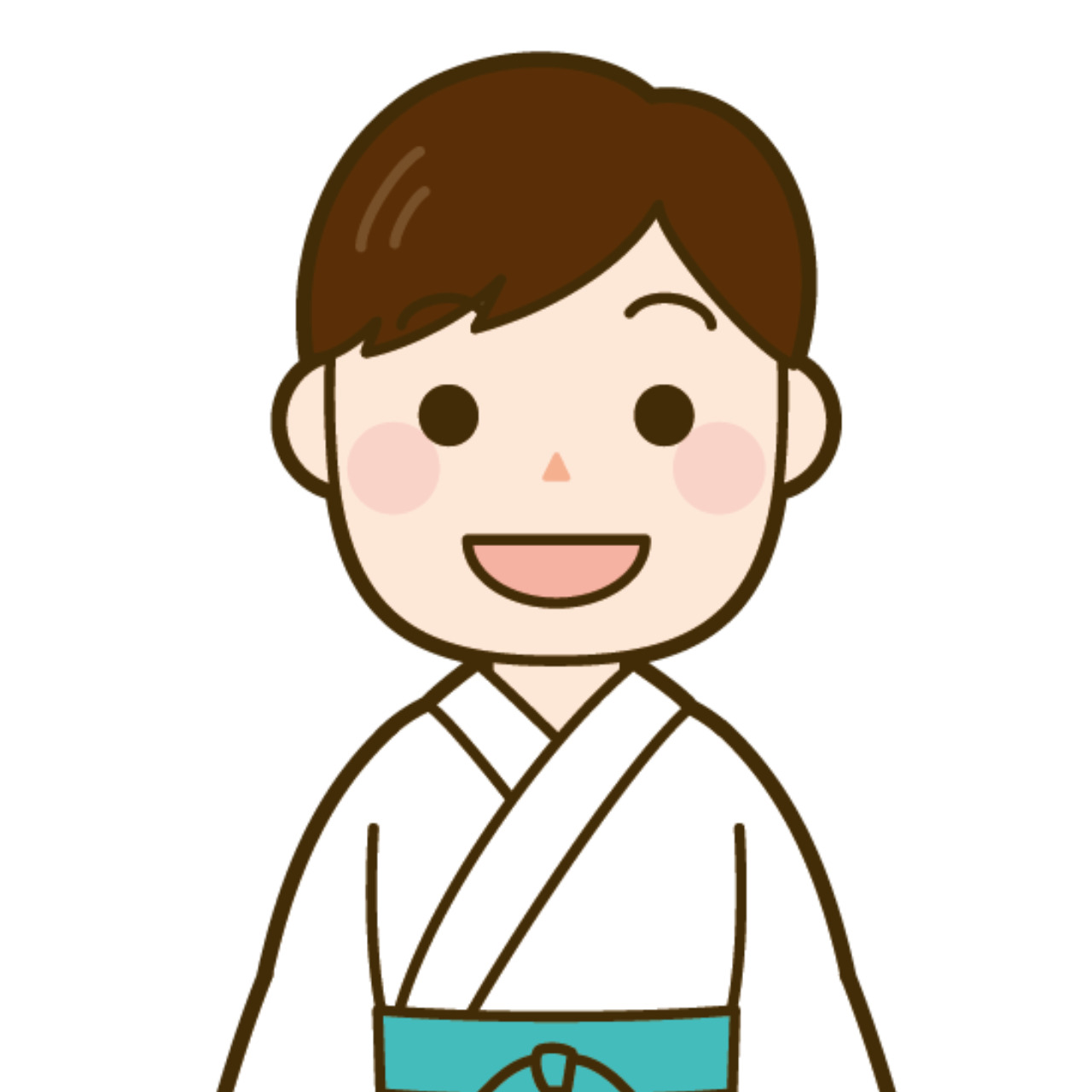
余談だけど…
あの有名な七福神には仏様である大黒天、弁財天、毘沙門天、布袋尊(弥勒菩薩の化身)、日本の神様の恵比寿天、中国発祥の道教の神様である寿老人と福禄寿で成り立っているんですよ!
神仏分離
神道と仏教は分けましょう
せっかく一緒にしようと広まった神社とお寺ですが、明治時代にはそれぞれの宗教を分けるべきだという考えが再度登場し、日本政府から神仏分離令が発令。
神仏習合で神社の中に造られた大部分の仏教関連のものは破壊されてしまいました。
その時に破壊されずに残った建造物が、現在の神宮寺や別当寺、宮寺などです。
建造物は壊されてもなお約1000年以上、人々の生活として根付いた神仏習合の習慣として消えることはありませんでした。
結局、お墓参りはお寺へ初詣には神社へといった感じで現代まで残っています。
こちらの記事もおすすめ✨
まとめ
今回は「『寺社』や『社寺』実際に何がどう違うのか」についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
なんだかとっても難しい話になっていしまいましたが、神仏習合によって『寺社』や『社寺』どちらも使われ、どちらも正しかったんですね。
違った信仰が混ざったり、離れたり…日本での信仰の歴史を振り返ってみることで、より深く日本の文化を感じることができるかもしれませんね。



コメント